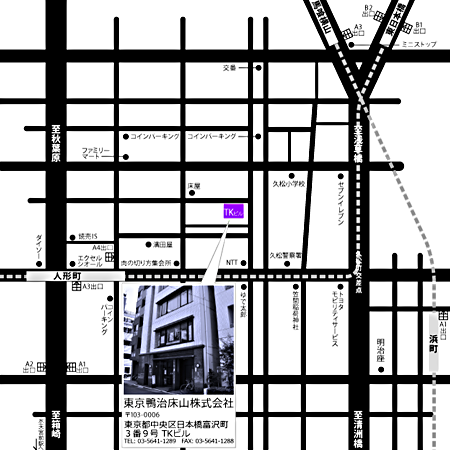(イントロダクション)
床山の仕事において何を良しとするかは、担当している俳優さんのお好みや、床山本人の役に対する解釈のみならず、時間の制限、運搬状況等々様々な要素があると思います。
それでも、本文中に「お前の仕事はどうも一閑張り(いっかんばり/和紙や布をを張り重ねて、柿渋や漆で仕上げた物)みたいでいけない」という表現があるように、きれいに整い過ぎた髪型が味気なく色気がない・・・というのはわかるような気がいたします。
ただ「水髪をよいとするのは主として世話物のあたまについていふのでして、時代物とかお家物のやうな油付の研ぎだしの髷をとりつけるものともなれば自ら手法も異り、水髪といふわけにはいかないものです。」ともあり、様々な美意識があるのが興味深いです。
【総務:鴨治】

歌舞伎床山芸談(三)-①水髪の味
明治時代に女形の名人として知られた上島宇之助師匠は、どちらかといへば大工仕事なみといはれるれるまでに荒削りな仕事をした人でした。
それでゐて女形の鬘(かつら)にかけては並ぶ者がない上手であつたといふのですから、やはり芸のふしぎな力によるものと見なければなりませんが、このかたがあるとき弟子を戒めていふのに、
「床山は、鬘にほこりがかかつてゐては恥だ。しかし髪が下つてゐるのは恥ぢゃない」
と言つたといふ逸話が残つてをります。
由来は弟子に大久保淸太郎といふ人があつて、この人が何でも日ごろから師匠とは反対に、ばかに油をつけて見てくれの綺麗な仕事をする。それがいかにも味気ないところから「お前の仕事はどうも一閑張り(いっかんばり)みたいでいけない」とたしなめたことによるものとのことですが、これはひとり上島師匠にかぎらず、そのころの師匠たち一般の仕事に対する心持をよく語つた、なかなか味はい深いことばではないかと思ひます。
そのころから見ると、今は舞台をめぐるいろいろな設備といひ機構といひ運営といひ、すべての点においてよく整へられて、四五十年前のそれとは比較にならないほどめぐまれた時世と申さねばなりません。
小屋には年中芝居がかかり舞台は休みなく廻つてをります。けれども、それでゐてわたくしどもの業界はどうかとかへりみるに、肝腎の仕事そのものは必ずしも技術的に向上してゐるとはいひがたく、むしろ年とともに時間的にも心持にもゆとりを喪つて、一般に手取り早い実利を追ふとでも申しませうか、すべてが小器用に、上島師匠のいはゆる綺麗ごとと化してゆくといふのがわたくしどもの偽らない感想であります。
姿かたちはいかにもよく整つてゐるが、どことなく生彩がない。よい色あひを呈してはゐるが味がない。さらに精巧にできてはゐるが、何となく自然味がない。
これをたとへていへば、極めて便利につくられた機械機構がかへつて新たな拘束となつて不便を生じるやうなもので、おたがひに近ごろの甚だめぐまれた忙しい仕組のなかでは、物を観る目にも作る技術にも余裕といふものがなくなつたといふのでせうか、何となく仕事に味がないのです。
もつとも、それにはかねてから材料に用ひる人毛その他の資材のよしあしの関係もあつて一概に昔と同日には論じられないところもあるにはあります。特に人毛によるそれはわたくしどもにとつて最も大きな痛手と申さねばなりません。
それといふのが、御承知のやうに鬘(かつら)は人毛を主な素材としてをります。それには昔から主として婦人の頭髪のぬけ毛であるとか斬り髪をあつめて使用してきた関係上、婦人が一般に毛髪を大切にして丈(たけ)なす黒髪をたくはへてゐた時分には問題がなかつたのですが、この節のやうにその風俗が一変して老いも若きもこぞつて断髪するやうになつてみると、鬘の材料にするやうな良い人毛が得られないのが当然で、近ごろでは特にその状況が悪くなつてきてをります。まるで無いといふわけでもありませんが、有つても昔のやうに充分丈のある人毛がとぼしい。そのために、一つの簔毛(みのげ/荒事等の鬘の生え際に用いる)を植ゑるにも長いのと短いのとが混つてゐるといふのが実情です。
したがつて、この短いのが散らないやうにまとめるには、どうしても油を使はないわけにはいきません。それには、何でもかまはず油でもつてかためてしまへば仕事は容易ですが、なるべく油によらないでサラッと結ひあげようとすれば、非常に優れた技術となみなみならぬ苦心を要すること言ふまでもないことです。
思ふに技芸のおもしろさといふものは本来そんな苦心工夫のうちにこそあるのでありませう。けれどもまた易(やす)きに就(つ)かうとするのも人情の一面で、近ごろのやうに次から次へと出し物に追ひかけられてみると、なかなかさういふ仕事のおもしろさをたのしむといふやうな余裕もなくて、つひ拙速(せっそく)となりがちなのもやむを得ないことです。
そんな関係から、この節の床山の仕事といへば立役のあたまであらうと女形のあたまであらうとむやみに油でかためて、ただ見た目に小綺麗であればよいとしてゐるところがないとはいへません。ひどいのになると抛(ほお)りだしてもちよつと形が崩れないまでに油でかためた仕事をする向きさへあります。これも時勢といへばそれまでですが、わたくしどものやうな昔風な者の眼からみればそれがいかにもをかしく、また飽きたらなく思へることでして、事実、また昔の名ある師匠たちはいづれもさういふ綺麗ごとを好まず、むしろ油などで仕事をするのを技の下(げ)として斥(しりぞ)けたものでした。そうして水髪のザングリした仕事のうちに物の自然な味はひであるとか色気であるとかをもたせて、それぞれの持味を生かす。そこに実は芸のおもしろさであるとか技の誇りであるとかいふものを見出してきたものでして、今とはずゐぶんちがふなあと思ふことです。そのこころといふものは、昔、仏師として名工のはまれが高かつた人が仏像を彫るのにやや鈍い刀を用ゐたといふことですが、どこかそれと相通じるものがあるのではないかと思ひます。
もつとも、ここに水髪をよいとするのは主として世話物のあたまについていふのでして、時代物とかお家物のやうな油付の研ぎだしの髷をとりつけるものともなれば自ら手法も異り、水髪といふわけにはいかないものです。
いづれにしても、うちの堀越師匠がやはりその流儀でしたから、稽古になかなか油などもらへませんでした。立役(たちやく)の鬘といふのは女形のそれとはちがつて、特にサラッと結ひあげたところに色気があるものでして、これがもし舞台で油光りしたりしたのではぶちこわしになるからです。
ですからわたくしなど修業時代にはめつたなことで油など使へず、ただ水髪でもつてきれいに結ひあげることにさんざん苦労を重ねたものでした。結ひあげるものが満足にできなくて油付の髷がうまくできるわけがない。それには水髪が基本をいふことです。
おまけに、そのころわたくしどもが使用する元結には、長尺のものを輪に巻いた輪元結と、一定の長さに切つて束ねた切元結といふのがあつて、侍物には輪元結、町人および女形の鬘には切元結ときまつてをりましたが、その元結も人によつては、こんど何々の役の鬘を結ふといふと必ず何本と数へて要るだけしか渡されないといふありさまでしたから、一つあたまを結ふにも実にいふに言へぬ苦心をしたものでした。
とにかくわたくしが小僧の時分の修業といふものは万事がそんな風でしたから、わたくしは今でも油をつける場合にはなるべく表面に見えないやうに隠して使ひ、あがりは水髪とあまり変わらないやうサラリと仕上げることにつとめてをります。けれども遺憾ながらこの節ではもうさういふザングリした仕事の味を解する人が少なく、ましてそんな仕事をしてみせる人も見かけなくなりました。何でも油でもつて形だけ綺麗に見えるやうに整へればよいといふことで、その結果、手のこんだ仕事をすればするだけかへつて不自然な、味も素気もないものにしてしまふといふのが一般です。これをいひかへれば、物を観る目においてもまた技倆においても昔と今では非常に大きな差異が生じてゐるわけでして、この点が時代の推移を感じさせる特に目立つた点といへば言へませう。