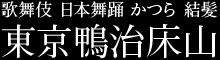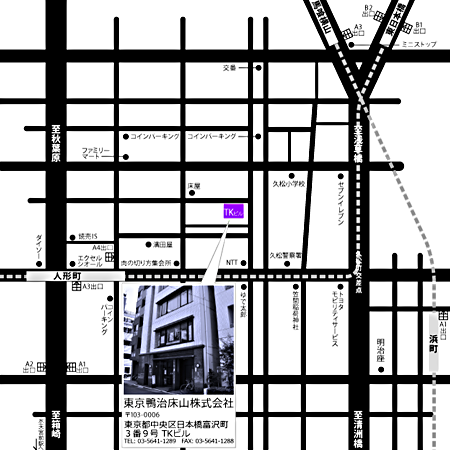針打という名前の髪型は、歌舞伎では立役と女形の両方にあります。
立役では「寿曽我対面」の曽我十郎祐成、女形では「羽根の禿」禿たよりや「助六由縁江戸桜」揚巻の禿等が代表的です。


立役の油付「針打」という名称の髷(まげ)は、古風な端敵(はがたき)役に用いる油付の「つぶ」という髷を大きく誇張した、「針つぶ」という髷と同様の手法で、それの根腰をとても高くし、ふくらみを柔らかくした物です。ふかし鬢と合わせて、棒ジケを付け、十郎の優しく色気のある古風な雰囲気を出しています。
女形の「針打」は主に禿の役に用いられます。写真の”禿たより”は、鬢上げ襟付きの針打で板ジケが付いており、可愛らしい髪形です。前差し、ピラピラ、槍梅、突き通し・・・と飾りも豪華で、髷には銀の飾りの付いた針(のような物)を差しています。立役とはかなり異なる雰囲気ですが、根腰がとても高いところは共通しているように思います。
真偽の程はわかりませんが、女形の「針打」について、興味深い逸話を聞いたことがあります。
江戸中期の辰松八郎兵衛という人形浄瑠璃の人形遣いが、自分の髷の刷毛先(はけさき)が人形に引っかからないよう、刷毛先を縮め、根を高く上げて髷を後頭部に向けて折り曲げて結い、その髷(まげ)に、人形の衣裳の引き抜きの際に留めてあった針を刺したておいたそうです。この根を高く上げた髪型が女髷に応用されたのが「辰松島田」で、それが後に「文金島田」となり、「文金島田」が髷に針を使っていたところから「針打」と呼ばれるようになったとか・・・。
時代は少し下がりますが、文化デジタルライブラリーに安永期頃の人形遣いを描いた錦絵「豊竹肥前座 乱菊枕慈童」があります。「刷毛先を縮め、根を高く上げて髷を後頭部に向けて折り曲げ」た髪型の雰囲気が感じられるように思います。歌舞伎 立役の「針打」とは違う形であることも興味深いです。
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_nishikie?division=search&class=nishikie&kw=%E8%B1%8A%E7%AB%B9%E8%82%A5%E5%89%8D%E5%BA%A7%E3%80%80%E4%B9%B1%E8%8F%8A%E6%9E%95%E6%85%88%E7%AB%A5&aid=16&did=1123194
(文化デジタルライブラリー 錦絵「豊竹肥前座 乱菊枕慈童」)
【那須正利】【写真:岩田アキラ】