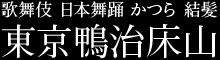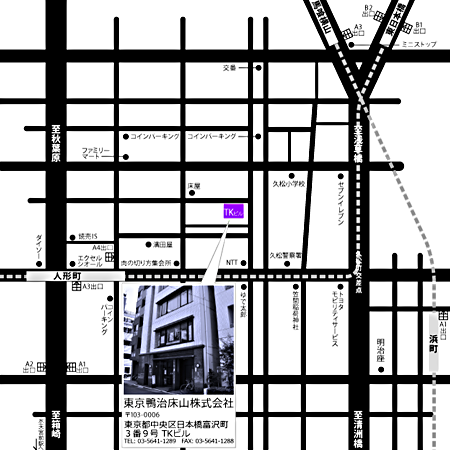(イントロダクション)
今回は、現在は行われなくなった床山の仕事について。
鴨治虎尾が明治35年生まれであったこと、又、文中に傳九郎丈のお名前がある事を考えても、大正の頃の話かと思われます。
但し歌舞伎俳優の地髪を結う仕事については明治以後には既に無くなっており、師匠の「昔ばなし」として記されています。
昔の楽屋の雰囲気と、床山の修業の様子が感じられて興味深いです。
【総務:鴨治(和)】【写真:岩田アキラ】
歌舞伎床山芸談(三)-④下地の話
(鴨治虎尾「歌舞伎床山芸談」第11回「口上の髷の話」つづき)楽屋銀杏に因(ちな)んで古いところでは「楽屋結び」といふのがあります。これは俗に「とんちき下地(したじ)」などともいつて、役者がまだ地(=地髪)の髷(まげ)をつけてゐた時分に楽屋で結つた髷のことで、今は見かけなくなつたものの一つです。
それといふのが、ごぞんじのごとく今日では舞台にでるのに役者はみな羽二重を頭に貼つて目吊りをしてゐます。けれども、あれは明治以後のことでして、それ以前に役者がまだ地髪(じがみ)を結つてゐた昔は一般に羽二重を用ひなくて、みな地髪に油を引き、それをぴつたりとあたまに貼りつけて目吊りの代りにしたものでした。
したがつて舞台がすむと役者は先づ鬘(かつら)を外して目吊をもどし、それから地髪をなでつけて小間結びに結ふわけですが、それを楽屋結びとかとんちき下地とかいつて、やはり床山が扱ふ仕事の一つとなつてをつて一定の型があつたといふことです。立役は小間結びに、女形は目鏡(めがね)といつて二つの輪に結んだといふのがそれであります。
いづれにしても、これは楽屋でのほんの一時しのぎのものであるうへに、明治以降は見られなくなつたものですから知る人も少ないことと思ひますが、そのほかに楽屋でなほ「しまひ髪」といつて、芝居が終ると、こんどは役者に全部髪を銀杏に結つて帰へすといふ仕事があつて、これも昔は床山の大切なつとめとなつてゐたものでした。
ところが、この「しまひ髪」にも床山によつてやはりうまいまづいがあるのはやむを得ないことでして、下手なのが結ふと、かう一束にとつた根締めが中剃にぴつたりくつついてこないものです。すると結はれた当人の方はいかにも気色がわるいところから、しきりにあれこれ小言をいふ。さうしてさんざんつぱら小言をいつて結ひ上げさせたあげく、気に入らないと刷毛先(はけさき)を持つて髷(まげ)をぐつと突込み「突込み」のまま帰つてしまふやうなことがよくあつたものだと師匠が昔ばなしに語つてをりました。まあ、意地が悪いといへば悪いやうなものですが、当人にしてみればこんな気持ちの悪い頭で帰れるものかといふところだつたのでせう。
この「突込み」といふのは、舞台では雲助(くもすけ)とか非人の役に用ひる見るからにをかしい髪形で、例へば『箱根の仇討』の筆助に用ひる「綯(な)ひまぜの突込み」とか『鈴ヶ森』の雲助に用ひる「すつぽり砂ずりの突込み」とか『梅の由兵衛』のどび六に用ひる「むしりの突込み」とか『四千兩』牢内の生き馬のがん八に用ひる「すつぽり水嚢(すいのう)の突込み」などといふのがみなそれです。かたちはいづれも髷(まげ)がこはれて根が落ちてきたのを、鬢(びん)をかきあげて無雑作に突込んだ恰好ですから、いかにも不精とも何とも見苦しいものです。

以上はいづれも明治以降一般に断髪が行はれて、楽屋髪の下地の代りに羽二重を貼るやうになつてからだんだん忘れられて行つたものですが、このほかになほ楽屋では役者のひげをあたるといふ仕事があつて、これも床山の大切なつとめの一つに数へられてをつたものでした。しかもこの方はわたくしが小僧の時分までずつとつづいてをりましたから、わたくしも早くからその修行をして、ずいぶんいろんなかたにあたつた経験があります。
このひげあたりには、人によつて化粧前(※註:楽屋の鏡台の前)であたるかたもあればお風呂のなかで湯につかりながら湯槽(ゆぶね)のふちを枕にあたらせる人もあるといふ風でまちまちでしたが、ただ幹部のかたはたいてい一日おきぐらゐにあたるのが例でした。したがつて長い楽屋つとめのあひだにはいろいろと思ひ出もあるわけですが、なかについて思ひだすのが傳九郎さん(※註:大正期に活躍した六代目中村傳九郎丈と思われる)のことです。この方はあたまを坊主にしてをられました。ですから、いつぞや襲名披露で名古屋から京都へかけて旅についていつたとき、頭とひげとを一日おきといふことで、今日はひげをあたつたら明くる日は頭といふぐあいに交互に毎日「なめ棒」(剃刀)を使つたことををかしく思ひだします。また格別ひげの濃いかたは「日なめ」といつて毎日あたることもありました。
しかし、このひげあたりもただ上手に剃刀が使ひこなせればよいといふものではありません。そこにはやはり一定の作法といふものがあつて、それが身に具(そな)はつてゐなければつとめられないとしたものです。たとへば幹部のかたのひげをあたるには、大方先方は化粧前(鏡台前)に坐るなり胡坐をかくなりしてゐるものですが、そのときこちらの足が俳優の膝より前へ出てはならない、また背中からかう頭を抱へこむやうにして下頤(したあご)をあたるとき、こちらの顔が俳優の顔を掩(おお)ふやうにあまり前へ突きだしてもいけないなどといふのがそれでして、さういふ作法が自然に身に具はつてこないとなかなかうまくいかないものです。ですから、その稽古にわたくしは師匠のひげをあたつてゐて、つひ足が膝より前に出たといつてはひどく向う脛をひつぱたかれたり、顔が前に出すぎるといふので煙管で額を突きあげられたりしたことが幾度かありました。
もつとも、かう言つたからといつて、稽古に師匠のひげのをあたるなどといふことはよほど剃刀を使ひなれてからの話でして、それまでには自身の膝小僧を膾(なます)になるまで稽古台としなければならないのがなかなかつらいことでした。
それといふのが、よく落し噺に髪床(かみどこ)の稽古には炮烙(ほうろく)の尻を使ふなどといふのがあるのですけれども、わたくしどもの稽古には自身の膝小僧を頭と見たてて稽古台に使つたものでして、それには先づ左の膝小僧を抱へこむやうにぴつたり胸につけて立て、もう片膝を折つた立膝の姿勢に坐ります。そうして頭は膝小僧、左の頬はふくらはぎの左側面、右の頬はふくらはぎの右側面、頤(あご)は向う脛といふ風に、考えてみれば実に理にかなつた方法で稽古の剃刀をあてるわけです。ところが、ご存知のやうにあの膝小僧といふのは特別ざらざらした肌をしてゐるものですから、そこへおぼつかない手つきで触れば斬れるやうな研ぎたての剃刀をあてたのでは、なかなかうまくいく道理がありません。あちこちが疵だらけです。しかも師匠はなかば面白がつて、時折剃刀を手にとつてみては「こんなので切れるか、もつと研げ」などといふありさまです。ですから、一時は膝小僧になま疵が絶えたことがなく、そんなことを毎日くりかへしてゐるとほんたうに膝頭が膾になつてしまふのではないかとやりきれない心地がしたものでした。今から考へるとずゐぶんをかしいやうですが、そんなことも昔は床山にとつて大切な修業の一つだつたのです。
なほ、ついでながら申添(もうしそ)へますと、剃刀を使ふにはただ手首だけの操作によるのでして、肱ひじ)を動かしたのでは、決してなめらかにあたれるものではありません。肱は常に一定の位置に安定さしておいて手首だけ軽く動かす、これが剃刀を使ふ場合の基本操作であり上手に使ふコツです。もしもこの要領によらないで肱から動かすと刄先に加はる力に自然とくるひがきて、あたりがむらになるばかりか、つい肌を傷つけたりすることがあるものですから危くて他人の顔などあたれたものではありません。しかもやさしそうに見えて、やつてみると案外むつかしいのがこの要領です。ですから、右のやうな稽古も、つまりは自分の膝小僧を稽古台としてその要領を会得することにあつたわけでして、作法上の心得などはすべてそれからのことでした。
いづれにしても、かうしてどうにか剃刀を使ひこなせるやうになつた者が、先づ最初に手がけるのは三階の大部屋のかたたちのひげ剃りときまつてゐて、幹部のかたにあたれるやうになるのはまだなかなかのことでした。つまり幹部にあたるのは、稽古といつては悪いのですが、三階で充分経験をつんでからといふわけです。したがつて大部屋がひと通りすめば先づ剃刀は一人前とされたものでした。
それから作法上のことで申上げれば、近ごろ髪床へ行くと、ひげをあたるのによく右の頬からあたるのに出会ひますが、あれは必ず左の頬からときまつたものです。どういふ理由からかよくは存じませんが、それがわたくしどもの方の定まつた作法でして、鬘(かつら)の鬢(びん)をとるのもやはり左からときまつてをります。また、床山が俳優のひげをあたるのも東京にゐるときに限られてゐて、旅に出たときには、必ずその土地々々の床屋が入つてきてあたる習慣になつてをりました。(但し幹部つきの床山だけは例外)それを「なめ屋」と称してをりました。これも由来はよくわかりませんが、おもしろい習慣であつたと思ひます。昔から縁起をかつぐこの社会では剃(す)るといふことばを忌んで、剃刀を「なめ棒」剃ることを「あたる」などと称してゐたのも格別のことと申せませう。
それもこれも、しかし時の流れとともに移り変つて今は昔噺となつて了ひました。安全剃刀といふものが出廻るやうになつてから俳優がだんだんと自分でひげをあたるやうになり、いつとはなしに熄(や)んだのであります。たしか関東大震災あたりを境として次第に廃れていつたのではないかと記憶します。従つて今は一般に床山の稽古は剃刀を研ぐことまでとなつてゐますから、以上申述べたやうな修業のつらさや作法を知る人は少ないことと思ひます。(つづく)