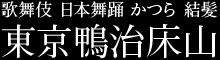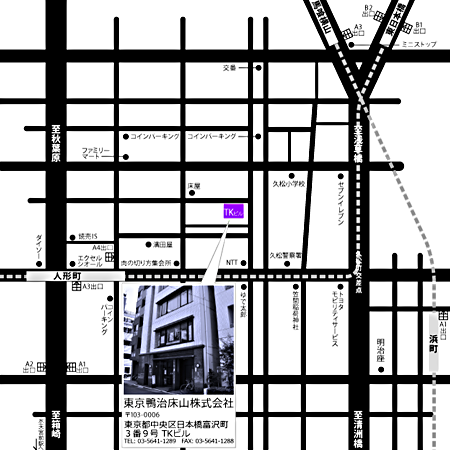(イントロダクション)
「歌舞伎床山芸談」は弊社創業者鴨治虎尾のインタビュー等をまとめた私家本で、内々の記念品として昭和58年につくられました。(詳細は連載の第1回目をご参照ください。)
後進の床山に対して話している内容も多く、又 あえて旧仮名遣いを残しておりますので、大変わかりづらいかと思います。
特に今回は「生締(なまじめ)」という歌舞伎立役 油付の髷(まげ)の中でも非常に重要な物がテーマなので、ボリュームもあり内容も専門的です。
そこで「生締の話」は四回に分けて少しづつ掲載することにいたしました。
一回目は「生締」の概要について。
弊社会長 鴨治欽吾の解説によりますと
「生締(なまじめ)という髷(まげ)は、助六・五郎・松王丸・工藤・仁木・石切梶原・実盛・粂寺弾正・八幡・男之助・熊谷等、これらの役々には全部それぞれの特徴があって、同じ形の髷を全ての役に使えるわけではありません。」
「『対面』の工藤の髷は工藤一役にしか使えません。根は細いのですが、元結を多く巻いて刷毛先にそりをもたせて折るのが特徴です。」

「盛綱(近江源氏先陣館・八段目)、『新薄雪』の園部兵衛、『いもり酒』の監物太郎は、『対面』の工藤と同じ「油付本毛込みの鬢羅紗張りの生締」という名称の髪型ですが、工藤に比べて髷が太く根が低く巻く元結が少ないです。これらの役々は基本的には同じ形の髷を使用できます。」

とのことです。
当時と現在では、多く用いられる形が変わっている役もあります。
例えば、『対面』工藤左衛門祐経は、現在「油付 本毛込みの(八枚)鬢 羅紗(らしゃ)張りの生締」が多く、立髪(たてがみ)やシッチュウが付く形はあまり見られなくなりました。
逆に『対面』八幡三郎行氏は「油付 本毛込みの(八枚)鬢 シッチュウ付の生締」がほとんどで、これは本文中にある『石段』の八幡の形です。

工藤を例にとりますと、昔から立髪 シッチュウの有無は、役の解釈や俳優さんのお好み等々様々な理由でバリエーションがあったようで、文化デジタルライブラリーのブロマイドには
七代目市川中車丈「立髪 シッチュウ共有り」、十五代目市村羽左衛門丈「立髪 シッチュウ共無し」の姿が残っています。
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=search&class=bromide&kw=%E5%B7%A5%E8%97%A4%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80%E7%A5%90%E7%B5%8C&did=302410
(文化デジタルライブラリー ブロマイド「寿曾我対面 工藤館対面 工藤左衛門祐経 / [7代目] 市川 中車」)
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/collections/view_detail_bromide?division=search&class=bromide&kw=%E5%B7%A5%E8%97%A4%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80%E7%A5%90%E7%B5%8C&did=302411
(文化デジタルライブラリー ブロマイド「寿曾我対面 工藤館対面 工藤左衛門祐経 / [15代目] 市村羽左衛門」)
【解説:会長 鴨治欽吾・聞き取り等:総務 鴨治(和)】【写真 :岩田アキラ】
歌舞伎床山芸談(四)-①生締の話Ⅰ
油付の髷(まげ)に「生締(なまじめ)」といふのがあります。主として実事(じつごと)・捌役(さばきやく)に用ひ、また荒事(あらごと)・敵役(かたきやく)などにも用ひることがあつてなかなか種類の多い髷(まげ)で、一般に町人の髷は銀杏(いちょう)に結ふのに対して、こちらは藺殻(いがら)を芯に毛をかぶせ油でかためて研ぎだしとするところに特徴があり、いはゆる時代物の立役の髷の基本的な型の一つをなすものですが、それには狂言も多いことであり役もさまざまです。
従つて時代と役がらとによつて、髷(まげ)の根腰(ねごし)の高低とか鬢(びん)のとりかた・月代(さかやき)のつくり・前髪の有無などにいろいろと工夫がほどこされてゐて、それがおのおの微妙に役の性根(しょうね)をあらはすやうになつてをるものですから、その仕分けのむつかしさはともかく、型をひと通り覚えるだけでもなかなかのこととされてゐるのがこの生締です。
たとへば髷(まげ)そのものについてみれば『対面』の工藤〈祐経〉とか八幡〈三郎行氏〉も生締なら、同じく『対面』の〈曽我〉五郎とか『金閣寺』の〈此下〉藤(東)吉・〈十河〉軍平なども生締です。
また『菅原伝授〈手習鑑〉(すがわらでんじゅてならいかがみ)』でおなじみの『車引(くるまびき)』の松王丸・桜丸も生締なら『石切〈梶原〉』の梶原とか『〈檀浦〉兜軍記』の重忠『源平布引瀧(げんぺいぬのびきのたき)』の実盛『〈熊谷〉陣屋』の熊谷〈次郎直実〉『助六縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』の〈花川戸〉助六といつた役どころもみな生締です。
けれども髷は同じく生締であつても『対面』の工藤と八幡三郎(やわたさぶろう)とではずゐぶん趣きがちがひますし、さらに五郎の頭ともなればご覧のごとく一段と趣向が変つてきております。
また時代は同じでも『石切』の梶原とか実盛と、『兜軍記』の重忠とか『近江源氏〈先陣館〉」の〈佐々木三郎兵衛〉盛綱とではやはり趣きがちがひ、下つて『先代萩』の仁木弾正(にっきだんじょう)とか『床下』の男之助の鬘(かつら)ともなればぐつと趣向が変つてきて、いかにもそれらしい役の性根とか強さをあらはすために元結一本・鬢のひと梳きにもいろいろと工夫をこらした古人の苦心のあとがうかがへるわけでして、そこに鬘の造形のおもしろさを観るべきではないかと思ひます。
このうち最もおとなしくて型通りなのが『対面』の八幡三郎とか『〈本朝〉廿四孝』の直江山城に用ひる「八枚鬢の生締」といふのでせう。これは髷の根腰も尋常で、ほかにこれといふ趣向もありません。
しかし同じく八幡三郎の役でも『石段』の八幡となると「本毛八枚鬢シッチウ付の生締」といつて、もみあげのところに櫛の歯を拂(はら)ふブラシに似たものがついてをります。これを「シッチウ」一名「櫛払(はら)ひ」などとも呼んで一般に役の強さをあらはす工夫になるもので、『対面』の工藤とか『戻駕』の次郎作とか『鎌髭』の妙典などの役にもそれが見られます。
ただしこの『石段』の八幡三郎と近江〈小藤太成家〉の役には一つの約束があつて、八枚鬢には簔(みの)のつくりと羽二重のつくりの二種類があるところから、八幡三郎がもし「簔(みの)のシッチウ付生締」でやれば近江は「雁金(かりがね)付研出(とぎだ)し燕手(えんで)の吉右衛門(鯰)」となり、八幡三郎が「羽二重のシッチウ付生締」でやれば近江も「研出し燕手」でなく「羽二重の燕手」でやることになつてをります。


なほ参考までに申添へますと、研出しといふのは地金の生え際の部分を研ぎだして、その光つた銅へ、羽二重に針で植ゑた通りに毛をそいで油で貼りつけるといふ非常に手のこんだ手法になるものです。したがつて「研出し燕手」といへば台金を研ぎだして燕手を貼つた意味で、これは床山が一種の道楽でやるといつてもいいやうな手間のかかる仕事です。
八枚鬢とはいはゆる小額(こびたい)のない鬢(びん)のことで、時代物または色気のある役に用ひて優しさをあらはすための鬢の型のひとつとなつてゐるものです。これに対して小額付(こびたいつき)といふのがあります。これは八枚鬢の優しさにくらべて強(きつ)く、敵役とか世話物にはおほむねこの鬢を用ひるのですが、ただ粋(いき)な役には小額の居どころを加減して位置を下げるのが普通となつてをります。
かうして見てくると、舞台でのつりあひとか、役の性根をあらはすために、刳り型や鬢のとりかたひとつにもずゐぶん細かな工夫がほどこされてゐることがおわかりになることと思ひますが、このほか荒事とか敵役に用ひてやはり強味をあらはすものに「立髪(たてがみ)」といふのがあります。この立髪といふのは甲羅(こうら)の際(きわ)へたてる短かい毛なみのことで、『対面』の工藤や『毛抜」の粂寺弾正をはじめ『鞘當(さやあて)』の不破・名古屋山三などにもそれが見えてをります。(但し『鞘當』の場合はこれも一つの約束があつて、不破が立髪付でやれば名古屋も立髪付、もし片方が立髪なしでやればもう一方も立髪なしといふことになつてをります。)
そこで『寿曽我対面』の工藤祐経の鬘(かつら)をくはしく申せば、鬢(びん)は本毛でもつて、甲羅(こうら)には羅紗(らしゃ)を張り、それに立髪(たてがみ)とシッチウがついて髷は生締ですから「本毛鬢羅紗(らしゃ)張り立髪シッチウ付の生締」といふことになりますが、髷(まげ)は細みでもつて根腰が高いのが特徴です。つまり同じく羅紗張りの生締といつても〈「壇浦兜軍記」畠山〉重忠などより根の元結の巻き数が多くなつてゐて、しかも髷(まげ)のつくりが細いわけです。従つてこの生締は「対面」の工藤くらゐのもので、他にはちょつと使ふ役のない髷といつてよろしいでせう。時代物の役でやはりシッチウ付の立髪付といふのに使へば使へないこともありませんが、先づその役がほかにないといふところです。
そこへいくと畠山重忠の「本毛羅紗張りの生締」は根腰の高さや髷の太さも尋常で、『阿古屋』の重忠『宮島のだんまり』の重忠をはじめとして、盛綱とか『〈新〉薄雪〈物語〉』の〈園部〉兵衛『切籠』の右馬之頭・和泉の三郎『玉取』の監物太郎などに同じに使へます。いづれもみな羅紗張りの生締でもつて、鬢(びん)もみあげがシッチウごころに少し厚く巻いてあるのが共通してゐるからです。
これに対して歌舞伎十八番のうちの『毛抜』の粂寺弾正(くめでらだんじょう)の生締も特徴のある生締で、やはりほかに例のない髷(まげ)といへませう。鬢(びん)や甲羅は『対面』の工藤と同じくシッチウが付き立髪があつてよく似てをります。けれども鬢の上にはちゃうど燕の翼のやうに髷の両脇へ出た「燕手(えんで)」といふものがついてをつて髷の根腰がずつと高く、その刷毛先(はけさき)が格別に反りをもつてゐるからです。これはほとんど粂寺弾正だけで他には見られない生締です。
また、燕手といふのはごらんのごとく主として敵役(かたきやく)とか凄味のある役に用ひて、文字通り凄味の効果をあらはすためのものです。

それには昔から唐毛(からげ=ヤクの毛)に漆を吹くとか、あるひはアラビア糊でかためるとかしてきたものでした。けれども漆を吹くならともかくアラビア糊でかためたのでは、ただ仕事が手つとり早いといふだけでいかにも味気がありません。それでいつそのこと少々手はかかつても研ぎだしにした方がいくらか時代がかつておもしろからうと思つて、わたくしは今月(昭和三十四年三月)の高麗屋(こうらいや)さん【註:初代松本白鸚丈/当時は八代目松本幸四郎丈】のを研ぎだし燕手にしてみましたが、果して効果はどんなものでせうか。試してみて自分ではこの方がずつと味があるやうに思つてをります。